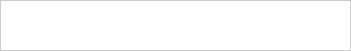《映像制作のシゴト》
中部クリエイティブ((株)中部電機) プロデューサー藤澤 勇さん・ディレクター藤澤由見子さん
演奏会の感動を記録する。かつての録音や写真(静止画)とともに、最近ではビデオ映像による記録もポピュラーになってきました。今回は、この道25年、舞台作品の記録映像を専門とするプロフェッショナル集団に、「こだわりの映像」についてお話を伺いました。


ーーー中部クリエイティブの事務所は、長野県岡谷市、JR中央本線の岡谷駅から少し丘を上った閑静な住宅地にある。1階が事務所兼編集作業場、2階が社長の藤澤勇さんと由見子さんご夫妻のお住まいという、究極の職住近接。オーケストラ、吹奏楽、合唱などの音楽作品やクラシック・バレエなど、いわゆる「舞台芸術」の映像制作に特化した企業だ。
1 出会いとご縁の連鎖
ーーー藤澤勇さんは、お父さんの代から家電販売店「中部電機」を営む。ソニーの特約店だったこともあって、音響機器に強い、いわゆる「オーディオ・ショップ」。自然と、録音やビデオ録画、それにそうした機材のメンテナンスの腕も磨いた。
その「中部電機」のお客さんでもあった由見子さんは、中学時代に合唱部で歌ったのち、卒業後はしばらく合唱から遠ざかっていたそう。1989年、岡谷市文化会館(カノラホール)の落成記念でベートーヴェン「第九交響曲」の合唱に参加、そこで中学時代の同級生と再会する。再び合唱の道に入り、お連れ合いの勇さんも合唱団で一緒に歌った。そして合唱団のつながり、口コミによって、録音や録画の仕事が徐々に広がっていく。
最初期のお客さんのなかに、岡谷合唱団の指揮者・佐原武さんと「女声コーラスしなの」などの指揮者佐原玲子さんがいる。岡谷の合唱界で長年にわたって中心的な活躍を続けるお二人だ。当時岡谷合唱団の常任指揮者だった関屋晋さんは、ときどき中部クリエイティブの事務所(当時は岡谷駅前にあった)に、ふらっと顔を出したという。この時代の藤澤さんご夫妻の記憶に残る仕事のひとつに《やさしさは愛じゃない》(谷川俊太郎/詩 三善晃/曲)がある。信州大学混声合唱団による初演。指揮は関屋晋。また、古い伝統をもつ合唱団「岡谷せせらぎ会」の創立40周年記念演奏会の映像も担当。合唱団にとっても、中部クリエイティブにとっても、こうした映像記録は「宝物」となった。
藤澤勇さん(以下「勇」)ベートーヴェンの「田園交響曲」を聴きながら、あれこれ想像して情景を思い浮かべる。そんなことが子ども時代から好きでした。エアチェック(FM放送をカセットで録音すること)をしまくっていました。なにせ家が電器店で、カセットテープだけは売るほどありましたから(笑)
ーーー勇さんは、子ども時代からのヘビーなリスナーだったそう。クラシック、ヘビメタ、それにピンク・フロイドなどのプログレ。そんななかでも、特に映画音楽が大好き。関光夫さんがDJを務めた映画音楽の番組をエアチェックしまくる。「音楽」と「映像」の関係のこだわりの塊である映画音楽に熱中した、というのが、今の勇さんの映像編集魂の元なのだろうか。
中部クリエイティブは、岡谷の企業でありながら、現在では、しばしば東京の合唱コンサートの収録も手がける。きっかけは佐原玲子さん率いる「女声コーラスしなの」に客演した作曲家・指揮者松下耕さんとの出会い。
藤澤由見子さん(以下「由」)ホールの収録では、舞台裏に機材をひろげて作業しているんです。どうも背後に人の気配があるなあと思ったら松下先生がこっちをずっと見ていらした(笑)。松下先生は、こんな作業をしているのか、とずいぶんびっくりされたそうです。で、たまたま仲良しの合唱団員がそこにいて、「この人たち(中部クリエイティブ)は、呼ばれたらどこへでも行くそうですよ」などと言う。それで、松下先生の合唱団のお仕事をいただくことになりました。
—出張収録はだいたいプロデューサー、ディレクターである藤澤さんご夫妻とカメラマン、総勢6、7人がチーム。大型ワゴン車に機材とともに全員が乗り込む。東京出張は中央高速で約3時間の旅。朝5時に出発し、9時前にはホール到着、終演後、岡谷への戻りは午前様ということも少なくないそう。
2 カメラマンのしごと
ーーー4、5台のカメラをホール客席内や舞台上に配置。原則、各カメラに撮影スタッフが付く。スーツにネクタイ姿。立っているし、場所によってはカメラの背後にもお客さんが座る。立ち姿も含め、お客さんに対する配慮が重要だ。
宮澤正さん 本番中、お客様にとっては、カメラマンというのは「居るだけで邪魔な存在」なんです。ですからカメラマンの仕事は、まず「気配を消す」ということです。
堀舜彦さん 吹奏楽などですと、音も割と大きいので多少楽な面もありますが、くしゃみ、咳は曲間でしておく。動きは最小限にして、変な動作はしない。そんなことが基本ですね。それと、開場してお客様が席に座る前からあらかじめスタンバイしている、っていうことも意外と大事です。後からスタッフが入ってくると、「なんだお前は」と思われてしまいがちですから。実は開演前からホールの天井を撮影したり、意外とやることは多いんですが、そういうときにお客様から声をかけられて困ったこともありました(笑)。
(勇)やはりお客様のほうも、「ああ、このスタッフたちは大事な仕事をしているんだな」っていうふうに、優しい眼で見てくださっているんだと思います。さいわい、今までのところお客様とトラブルが起きたことはあまりありません。
ーーー舞台裏で司令塔として各カメラマンに出すディレクターの指示は、インカムを通じて各スタッフに伝える。カメラマンは客席や舞台上にいるので、カメラマン側からは喋れない。インカムは舞台裏からカメラへの一方向通信となる。ではカメラマンから何か言いたいときはどうするか?
堀舜彦さん「わかった」という時はカメラを縦に、「きこえない」とか「いやだ!」という時は横に振ったりします。それでも通じないときは紙に字を書いてカメラの前にかざすんです(笑)。

3 映像は言葉と、そして呼吸とシンクロしている
ーーーテレビやDVDで観る映像番組と同じく、いわゆる「マルチカメラ」といって、複数のカメラで同時に収録し、編集がされている。いろいろな角度からの映像、指揮者やソリストの姿、パン(クローズアップの画像が横に移動していくこと)で合唱団全員の顔をなめていくなど、変化に富んだ映像が、音楽映像の醍醐味だ。この、いろいろなカメラで撮った映像を順次切り変えていく編集を「カット割」あるいは「カメラ割」という。
あらかじめ楽譜を緻密に読み込み、カット割を指示表(スクリプト表)として作成する。演奏中、リアルタイムでこのカット割に基づいてカメラを切り替え、また各カメラマンが次の場面でどこにカメラを振るかの動きを決める。演奏中の舞台裏には、4台のカメラから送られる映像がモニターに映し出されている。由見子さんが楽譜に書き込まれたカット割りのキュー(合図)を、小節数のカウントとともに読み上げ、となりの勇さんがカメラのスイッチを切り替えていく。松下耕さんが見て驚いた、というのがこのお二人の連携作業だ。では、曲のなかでカットを切り替えていく、カメラ割という作業はどのように決めていくのだろうか?
(由)合唱曲の場合でいうなら、カメラ割の99%は「言葉」によっていると言って過言ではないと思っています。詩人の思いが「詩」となり、そこに作曲家の思いがあって「歌」「音楽」が成立しています。作曲家は、詩を読み込み、詩人が伝えたい言葉がいちばん引き立つように音楽を書いていると思うんです。一番大事な言葉が楽譜上のどこからどこへと移っていくのか。楽譜からそれを読み込んで、書き込んでいく。それが撮影前の準備作業です。
外国語の曲の場合は訳詩(逐語訳)で理解します。音源がある曲なら必ず聴きますし、初演作品であれば事務所のピアノで弾いてみたりもします。
ーーーこの、由見子さんが楽譜上でアナリーゼ(分析)した結果は、カメラごとの指示表へも展開されていく。

(勇)本番は、言ってみれば「計画に沿って撮る」だけといってもいい。事前のこの「計画づくり」にほとんどのエネルギーを注いでいるんです。場合によっては合唱団の練習に事前に伺って合唱団のニーズをくみとり、現場の下見もしたうえで、こうした楽譜の読み込みをします。あるオーケストラの映像専門のチームの話を聞いたことがあるんですが、彼らも収録の前には1ヶ月もその演目を聞き込んでいるそうです。やはり同じだなと思いました。
そしてコンサートの全体像を頭に入れた状態で本番に臨む。東京出張に行くときは車内で3時間ありますから、その間にも車内で音楽を聴いて、スタッフ全員で共有しています。全体像がわかって、これはいいコンサートになるぞ、と思うと、みんなだんだんわくわくしてくるんですよ。やはり余裕をもって現場に臨みたいですね。もっとも実際には、現場ではいつも戦争のような状態ですが(笑)。
ーーー合唱は、オーケストラや吹奏楽と比べると編成が身軽なぶん、ホール入りからリハーサル開始までの時間が短い。カメラやモニターの器材セッティングは慌ただしく、まさに戦場のようだ。
ゲネプロ(通しリハーサル)で、事前の計画に沿ってひととおり撮影する。すると、なかなか計画通りにはいかない箇所も出てくる。例えば後列に背の低い人がいて、その人が映らないということもままある。ゲネプロ後には、チームが集まり、気になったシーンについてディスカッションし、カメラ割りを変えるなど、計画を手直ししていく。
(勇)基本的には、一曲のなかでできるだけ全ての団員さんが最低一度は映っている、というように心がけています。子どもさんの合唱ですと、特に「平等」ということに気を配ります。学校の合唱ですと、ご家庭の事情などで撮影不可、という生徒さんもいたりするので、そういった配慮も必要です。いっぽう大人の合唱ですと、多少芸術性優先でもいいかな、と、お客様によってもかわってくる。
あくまで依頼者である演奏団体のみなさんの満足度が第一です。私たちは、演奏団体の代行として記録をしているという立場なので、自分の主張よりもまずお客様のニーズ優先です。できるだけお客様とのコミュニケーションを深めて、相手の気持ちやニーズをくみとる、ということが大事だと思いますね。
何度も仕事をいただいているうちに、合唱団のメンバーの方々と仲良くなってきます。そうすると、いろいろなリクエストが出てくるんです。カット割りの好みからはじまり、「恥ずかしいから、私はあまりアップで撮らないで!」「私の顔は右からでなく、左がいいので宜しく」などなど。こうした情報も、技術の蓄積の一部なんです。
ーーーさて、事前のカメラ割りの計画、そしてゲネプロでの修正を経て本番を撮影。これで業務完了かと思えばそうではない。後日、事務所での編集作業が待っている。字幕を入れるなどの作業に加え、現場で行ったカメラ割りの微修正もする。
(勇)いくら事前の計画があっても、どうしてもカメラの切り替えのタイミングは、現場では完璧にはできません。あるカットから別のカットに切り替えるタイミングや速さを微調整する必要があるんです。
ビデオカメラというのは、1秒間に30フレームの画像を撮影しています。この1/30秒の違いが重要なんです。1フレーム前でも、1フレーム後でもない、この瞬間に切り替える、という手直しをしていくわけです。で、その切り替えのタイミングを計るうえで一番重要な情報は、指揮者が出すアインザッツ(フレーズの出だしなどの合図)です。指揮者のアインザッツの出し方は、歌い手の呼吸のスピードにもつながっていて、それらに映像の動きが同調するわけです。カットの繋ぎ方もそうですが、字幕の文字が現れて消えるタイミングも、すべて音楽の呼吸に合わせて変えています。
4 作品にとっての「額縁」になりたい
(勇)先日、東京に所用があって行ったとき、上野の美術館でフェルメール展を見たんです。すごい人だと思った。カメラもなにもない時代に、命を削って対象をリアルに手描きで記録したわけですから。そこでふと思ったのだけれど、今年の目標は「額縁精神」にしようと。
僕らはフェルメールの作品そのものを鑑賞しているわけで、ほとんどの人は、額縁は意識しては見ていないですよね。でも、額縁は、それ自身主張はしないけれど、作品の一部には違いない。そう考えてみると、フェルメールの絵に当たるのが楽曲や演奏で、私たちの映像は額縁にあたるんじゃないか、と。楽曲、それに演奏家を活かすために映像がある。それがわかっていただける人に対して、とことんそこを追求してみたいな、と思っています。
ーーー2011年にはハイビジョン対応のため機材を一新した。「全財産をはたいて、いまだに元はとれていません(笑)」と勇さんはいう。このとき、ある放送用機材の専門メーカーが、中部クリエイティブの仕事の特徴に合わせて、器材のカスタマイズをしてくれたという。
(勇)メーカーの技術者さんが、わざわざうちの仕事現場に見にきて、どういう改良をしたらいいか考えてくれた。「将来に期待しています」と言ってくださったんです。本当に我々は、いろいろな方々に生かされているんだなあと感じます。
ーーー映像器材は、現在では4K、8Kとどんどん進化しているが、藤澤さんは画像情報の「量」ではなく「質」にこだわる。
(勇)4K、8Kというのは走査線の数、情報量が多いということで、それだけ大画面でもきれいに画像を見られるわけですが、実はそれは画像のクオリティとは少し違うと思うんです。明るい部分から暗い部分までのダイナミックレンジの広さや階調の豊かさ、それに人肌の色合い。こういう「質感」に私たちはこだわりを持っています。どんどん技術革新が進むのは、産業としてそれはそれで必要なことかもしれませんが、私たちはそういった経済の都合には振り回されたくない。
音楽はその場で消えていってしまうもの。それを記録としてとどめるのが私たちの仕事です。演奏会の後に誰かの家に集まって映像を見て大いに盛り上がる、というのは楽しいですよね。できれば一回観てもういいや、ではなく、繰り返し観たくなる、そんな映像を残したいんです。ホンモノと言ってもらえるものを提供したいですし、私どもの映像を「宝もの」と呼んでいただけたら光栄です。
音楽作品の最も古い記録物は「楽譜」です。技術の発達につれて、録音が残されるようになった。今では「歴史的録音」と呼ばれるような貴重な財産が残されているわけですが、私たちも、後年、「歴史的映像」と呼ばれるようなものを残したいなと思っています。
しかし、いくら追求しても、正解は一つではないので、到達点というものがないですね。25年この仕事をやっていて、手ごたえはそれなりにあるのですが、いまだに「会心作」と呼べるものはないなあ。だからこそ、みんなで「ガンバロー」って言えるのかもしれませんが。

(2019年1月16日 中部クリエイティブ事務所でインタビュー A.Y)